
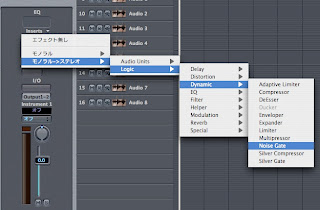
logic proでのゲートの件。
今回はシンセなどの音色素材Aをリズムなどの音色Bでゲートで切る設定を解説。
とある友人から説明を求められたのですが、メールで説明する労力を超えているのし
もったいないのでupします。
そして文字だけで説明できるかちょっと不安。
切りたい音色素材Aは今回、シンセベースにしましょう。
Instrumentのトラックでも、Audioトラックでも良いです。
適当に2小節くらいサスティーンする音色とデータが好ましいです。
この例では切る側の音色Bは4つ打ちのキックにします。
キックに合わせて切る、とはどういうことか。
それはキックBが鳴るとベースAが聞こえなくなる、ということです。
分かりやすく「切る」とココでは言ってますが、
Dynamics>Noize GateプラグインのReductionのレベル設定によっては
「切る」だけでなく「ちょっと下げる」や「逆に上げる」などの効果も出来ます。
音色ベースA「ブーーーーーー」
音色キックB「ドンッドンッドンッドンッ」
が「ドンブードンブードンブードンブー」と鳴ります。
ベースを8部音符裏で打ち込めば同じ、ですが
それとは明らかに違うネバリというかグルーブが演出できます。
工程の説明に戻ります。
・切りたい素材AのトラックにPlug-in>Dynamics>Noize Gateをインサート。
・キックBがInstrument TrackであるならばOutputをBusに設定するか、
センドでBusに送ります。
・その理由は、NoizeGateのSidechain入力を使うためです。
インサートされたAをSidechain入力されたBで動作させるためには
Instrument Trackからの音声入力は入力選択に表示されないからです。
音声BはInstrumentならBusへ。
音声BがAudio Trackならそのままで大丈夫。
・NoizeGateのThreshold LevelとReduction Levelを調節します。
Reduction Levelは最初は-99位の分かりやすい値にしておいてから
Thresholdをいじると効果が分かりやすいです。
・この場合、Busに出力されたキックBを実際に音楽や楽曲の一部として出力するかしないか、は
曲やアレンジによります。
曲で使っているキックなどを素材にして上記の動作をさせれば
その曲のキックのフレーズに合わせた動作することになるので、
キックが休みの部分で、ベースAがある場合などはGateは動作することが無いので
鳴りっぱなしになります。それが良いか悪いかはその曲やアレンジしだいです。
・これを応用すると、完成したダンスミュージック系の曲で、どうもキックが前に出てこない。
どんなにバランスをとっても上手くいかない、などの時に応用できます。
キック以外のオケをA、キックをBとしてGateやLimitter/CompressorのSidechain入力で
動作させると、キックが鳴るたびにオケのレベルの上下をコントロール出来ます。
ま、若干オケが下がる程度にしておきましょう。
(この場合、Reduction Levelを最低にしてしまうとキックが鳴るとオケが無し、
という実験的なミックスの領域に入ってしまうので注意)
説明より余談が多かったですが、どうですか分かりますかね?
フィードバックをお願いします。
1 件のコメント:
親切な解説ありがとうございましたー!無事に出来ました!!
コメントを投稿